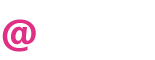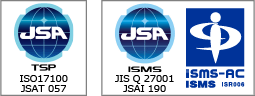フリーランス通訳の料金相場は?失敗しない依頼方法と料金表を公開
ビジネスのグローバル化が加速し、企業として通訳が必要となる場面が増えてきました。しかし、いざ通訳を手配する段になると、「料金の相場が全く読めない」「フリーランスと通訳会社、どちらに頼むのが正解なのか?」といった未知の領域に、多くの担当者様が頭を悩ませています。
通訳の費用は、案件の性質によって大きく変動します。そして、誰に依頼するかという選択は、時にビジネスの成果そのものを左右するほど重要な決断となります。
この記事は、プロジェクトマネージャー、イベント主催者、そして企業の意思決定者の方々が、通訳手配のプロセス全体を自信を持ってナビゲートできるよう作成した、包括的なガイドです。最後までお読みいただければ、以下の点をご理解いただけるでしょう。
- 通訳の種類とそれぞれの特徴・適したシーンを理解できる
- 通訳 相場 フリーランスの料金水準と価格決定要因を把握できる
- フリーランスと通訳会社の違いや選び方を理解できる
- 通訳依頼の手順と必要な準備事項を理解できる
通訳の3つの種類と最適なシーン

通訳の相場って、まさに“フライトの座席”みたいなものです。同じ目的地に向かうのに、エコノミーからビジネス、ファーストクラスまで幅広い選択肢があって、それぞれの値段もサービスも全く違います。
とはいえ、自社のニーズに合った通訳者を雇うためには、そんな通訳相場の理屈と依頼方法を理解しておく必要があります。
通訳相場を理解するための大前提として、まずは通訳には代表的な3つの形式があることを知っておきましょう。
逐次(ちくじ)通訳
話者が一区切り話した後に、通訳者がその内容をまとめて訳す、最も標準的な形式です。話者が話している間、通訳者は内容を記憶し、正確に再現するためのキーワードをメモに取ります。
長所: 通訳者が思考を整理し、最も正確な言葉を選ぶ時間があるため、情報の正確性が非常に高いのが最大のメリットです。
短所: 話す時間と訳す時間が必要なため、会議全体の時間は約2倍になります。スピーディーな進行が求められる場面には向きません。
最適なシーン: 契約内容を一条ずつ確認するような法務関連の会議や、質疑応答が中心のインタビュー、少人数での重要な商談など、一言一句の正確性が最優先される場面で最も効果を発揮します。
同時通訳
専用の機材(通訳ブースやヘッドフォン)を使い、話者の発言を聞きながら、2〜3秒遅れてほぼ同時に訳していく高度な技術です。通訳者は、脳内で「聞く」「内容を理解する」「別の言語に変換する」「話す」という4つの作業を同時に行うため、極めて高い集中力と認知能力が求められます。
長所: 会議がスムーズに進行し、時間を大幅に短縮できます。聴衆の集中力を維持し、イベントのテンポを保つことができます。
短所: 高度なスキルが必要なため通訳料が最も高額になり、専用機材のレンタル費用も別途必要です。
最適なシーン: 多数の聴衆が参加する国際会議やシンポジウム、限られた時間で多くの議題をこなす必要がある株主総会など、時間の効率性が重視される大規模イベントに不可欠です。
ウィスパリング通訳
通訳を必要とする1〜2名の聞き手のすぐ側で、ささやくように同時に通訳する、同時通訳の一形態です。
長所: 専用機材が不要で、特定の人物だけをピンポイントかつ静かにサポートできます。
短所: 静かな会議室ではささやき声でも周囲の妨げになる可能性があり、物理的に1〜2名にしか対応できません。
最適なシーン: 海外からCEOを一人だけ招いて社内会議に参加してもらう際の役員随行や、工場視察で技術的な説明を特定の人物にだけ補足する、といった場面で活躍します。
これら3つの形式をまとめると、以下のようになります。
| 通訳形式 | 概要・特徴 | 長所(メリット) | 短所(デメリット) | 最適なシーン |
| 逐次通訳 | 話者が区切った後にまとめて訳す、最も標準的な形式。 | ・情報の正確性が非常に高い | ・会議全体の時間が約2倍になる | ・商談 ・インタビュー ・法務関連の会議 |
| 同時通訳 | 専用機材を使い、話者とほぼ同時に訳す高度な形式。 | ・時間を大幅に短縮できる ・会議がスムーズに進行する | ・料金が最も高額 ・専用機材の費用が別途必要 | ・国際会議 ・シンポジウム ・株主総会 |
| ウィスパリング | 聞き手の耳元でささやくように訳す、少人数向けの形式。 | ・専用機材が不要・特定の人だけをサポート可能 | ・対応人数が1〜2名と限定的 ・周囲の妨げになる可能性 | ・役員の随行 ・工場視察 ・特定の人物への補足説明 |
では次に、通訳を依頼する時に迷うこの問題です。つまりフリーランスに頼むのか、通訳会社から通訳者を派遣してもらうのか、という点です。順にみていきましょう。
フリーランスと通訳会社、どちらを選ぶ?

フリーランスと通訳会社、どちらを選ぶのかという点ですが、まずどちらか一方が良い、というわけではなく、目的に合った通訳者を選ぶのが正しい、と理解しておきましょう。
つまり、案件の「リスク許容度」「予算」「かけられる手間」という3つの軸で、自社に最適な選択肢は変わる、ということです。
それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| フリーランスに直接依頼 | 通訳会社に依頼 | |
| メリット | ・中間マージンがなく比較的安価 ・柔軟な交渉が可能 ・同じ人に継続依頼しやすい | ・案件に最適な人材を提案してくれる ・品質が担保されている ・急な交代などトラブル対応が安心 |
| デメリット | ・探す手間がかかる ・品質の見極めが難しい ・急なキャンセル時の代替が困難 | ・中間マージンが発生し高め ・担当者が毎回変わる可能性がある |
比較的コストが低く、それでいて経験のある通訳者に巡り合うのは簡単ではありませんが、案件を依頼するかどうかを決める前にチェックしておくと良い点をご紹介します。
良いフリーランス通訳者を見極める3つのポイント
もしフリーランスへの直接依頼を検討するなら、以下の3つのポイントで候補者の「真の実力」を見極めましょう。
実績の確認
「IT分野の経験はありますか?」という漠然とした質問では不十分です。「過去にどのようなIT関連の会議や商談を通訳されたか、差し支えのない範囲で、具体例をいくつか教えていただけますか?」と一歩踏み込んで質問しましょう。具体的な回答ができるかどうかで、経験の深さが測れます。
コミュニケーション能力
メールの返信は迅速で、文章は丁寧で分かりやすいか。こちらの意図を正確に汲み取り、先回りして確認してくれるか。こうした事前のやり取りの質は、本番でのパフォーマンスに直結することが多いです。ビジネスパートナーとして信頼できる人物かを見極めましょう。
「準備」への姿勢
良い通訳者の最大の特徴は、準備への貪欲な姿勢です。こちらが資料を送るのを待つだけでなく、「参考になる過去の議事録はありますか?」「主要な参加者のプロフィールをいただけますか?」など、積極的に情報を求めてくる通訳者は、プロ意識が高い証拠です。
では次に、フリーランスではなく通訳会社に依頼すべき場面についてです。
通訳会社に依頼すべき3つの場面
フリーランスへの依頼は魅力的ですが、リスク管理や効率を考えると、通訳会社に任せるのが賢明なケースもあります。
専門性が高い、失敗が許されない重要な場面
新薬の承認に関する最終会議、大型M&Aのデューデリジェンス、特許侵害訴訟の証人尋問など、通訳の質がビジネスの結果、ひいては企業の未来を直接左右するような場面です。このようなハイリスクな案件では、費用よりも「確実性」を優先すべきです。
通訳会社は、厳しい基準でスクリーニングしたトップクラスの専門家を確実に手配できます。これはコストではなく、「安心」という価値への投資と考えるべきでしょう。
複数名の通訳者が必要な場合
同時通訳では通常2〜3名が1チームで対応しますが、そのチームワークは非常に重要です。通訳者同士のスキルレベルや専門知識、さらには声のトーンや話すテンポの相性まで考慮する必要があります。
これをクライアントが自力で判断し、個別に契約を結ぶのはほぼ不可能です。通訳会社に依頼すれば、実績のある最適なチームを編成してくれます。
手配にかける時間がない場合
担当者が本来の業務で多忙な場合、通訳者を探し、何人もの候補者とメールをやり取りし、スキルを評価し、条件交渉や契約手続きを行う時間は、想像以上に大きな負担になります。通訳会社は、その煩雑なプロセスすべてを代行してくれる、いわば「外部の専門チーム」です。
万が一、アサインされた通訳者が急病などで対応できなくなった場合でも、代わりの人材を迅速に手配してくれるバックアップ体制は、フリーランスへの直接依頼にはない大きな魅力です。
弊社アットグローバルでは多くの経験を積んだプロの通訳者が在籍しています。
ではいよいよ、フリーランス通訳の相場について見ていきましょう。
フリーランス通訳の料金相場

通訳料金は、主に「通訳者のクラス」「専門分野」「言語」という3つの要素の掛け合わせで決まります。それぞれの要素がどのように価格に影響するのか、詳しく見ていきましょう。
通訳者のクラス別料金相場
通訳者の料金に最も大きく影響するのが、フリーランスとしての経験値です。これは単に「年数が長い」ということではなく、「どれだけ専門性が高く、責任の重い現場を成功に導いてきたか」という信頼と実績の証です。
| クラス | フリーランス経験(目安) | 1日の料金(8時間拘束) | 主な対応業務・スキルレベル |
| Sクラス | 10年以上(トップレベル) | 120,000円 ~ | ・政府間会合、首脳会談など国家間の重要案件 ・訴訟、特許、医療など極めて高度な専門分野 ・業界の第一人者で、指名で依頼が入るレベル |
| Aクラス | 10年以上 | 80,000円 ~ 120,000円 | ・大規模な国際会議、専門的なシンポジウム ・企業のM&Aや重要な契約交渉 ・安定して高いパフォーマンスが求められる場面 |
| Bクラス | 5年以上 | 50,000円 ~ 80,000円 | ・企業内のビジネス会議、セミナー、研修 ・記者会見、製品発表会 ・特定の専門分野の基礎知識を持つ |
| Cクラス | 1~5年 | 30,000円 ~ 50,000円 | ・展示会でのアテンド、簡単な随行 ・空港送迎、会食の同席 ・日常会話レベルの逐次通訳 |
コスト管理はもちろん重要ですが、企業の命運を分けるような商談で費用を最優先し、経験の浅い通訳者を選んだ結果、微妙なニュアンスが伝わらずに交渉が決裂した、という事態は絶対に避けなければなりません。
重要な案件ほど、AクラスやBクラスの通訳者への投資は、リスクを回避し成功確率を高めるための合理的な経営判断と言えるでしょう。
こうした場面では、初めて依頼するフリーランスではなく、多数のプロの通訳者をかかえる通訳会社に依頼した方が、リスクを回避することができます。
「シーン・専門分野」別料金相場
「一般の医師に脳外科手術を頼まない」のと同じように、通訳者にもそれぞれ専門領域があります。専門性が高い分野ほど料金が高くなるのは、単に専門用語を知っているからではありません。その背景にある業界の文脈、規制、最新の技術動向といった、目に見えない知識体系を理解しているからです。
(高)医療・医薬、金融、法律、IT、特許
例:臨床試験に関する会議、M&Aのデューデリジェンス、特許侵害訴訟など。
理由:一つの誤訳が、人命や莫大な金銭的損失、法的な責任問題に直結する可能性があるため、最高レベルの正確性と専門知識が求められます。
(中)ビジネス全般、IR、マーケティング
例:社内の定例会議、製品発表会、投資家向け説明会、市場調査インタビューなど。
理由:一般的なビジネス知識に加え、企業の戦略や財務状況、交渉の機微を理解する能力が求められます。
(低)一般アテンド、観光
例:空港送迎、会食の同席、市内観光など。
理由:高度な専門知識よりも、円滑なコミュニケーション能力やホスピタリティが重視されるため、比較的対応できる通訳者の層が厚くなります。
「言語」による料金の違い
需要と供給の原則に基づき、話者人口の少ない言語や、ビジネスでの使用頻度が低い言語は、対応できる通訳者の数が限られるため料金が高騰します。例えば、技術交渉のために日本語とスワヒリ語の通訳者を探すのは、同じ内容で日本語と英語の通訳者を探すよりも格段に難しく、費用も高くなります。
通訳以外に発生し得る費用

正確な予算を組むために、基本料金以外に発生しうる費用をチェックリストとして確認しましょう。
交通費・出張旅費
通訳者の自宅から会場までの往復交通費です。新幹線や飛行機での移動が必要な場合は、その実費も含まれます。
確認ポイント: 見積もりに実費と記載されているか、それとも定額が含まれているかを確認しましょう。
宿泊費・日当
遠方への出張や、早朝・深夜の業務で宿泊が必要な場合に発生します。
確認ポイント: 宿泊先をクライアント側で手配するのか、通訳者自身が手配し後日実費精算するのかを事前に決めておきましょう。
移動拘束費
長距離の移動により、通訳者がその日一日、他の仕事を受けられなくなる時間を補償する費用です。
確認ポイント: 「移動時間が片道2時間を超える場合」など、適用条件を見積もり段階で明確に確認しておくことが重要です。
機材費
同時通訳に必要な通訳ブース、マイク、ヘッドフォン、赤外線送信機などのレンタル費用です。
確認ポイント: 通訳会社に依頼する場合、機材の手配から当日のオペレーター派遣まで一括でお願いできるか確認するとスムーズです。
高価な機材が必要な通訳の場合、フリーランスに依頼するのはリスクがあることを念頭に置いておきましょう。
二次利用料
通訳中の音声を録音・録画し、社内研修資料やWebで一般公開する場合に発生する著作権関連の費用です。
確認ポイント: 録音・録画の可能性がある場合は、必ず事前に通訳者やエージェントに申告し、利用範囲(社内限定か、一般公開か)を伝えて料金を確認してください。無断での公開は契約違反となり、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
依頼から当日までの流れ【5ステップ】
依頼先が決まったら、最高のパフォーマンスを引き出すために、以下の流れでプロジェクトを進めましょう。
【ステップ1】要件の整理(依頼前の準備)
問い合わせをする前に、依頼内容をできるだけ詳細に言語化しておきます。「日時、場所、言語、通訳形式、テーマ、参加者の役職と人数、当日のアジェンダ案」などをまとめた依頼シートを作成すると、その後のやり取りが非常にスムーズになります。
【ステップ2】問い合わせ・見積もり依頼
候補となる個人や会社に連絡し、見積もりを依頼します。この際、単に見積金額だけでなく、質問への回答の速さや的確さ、提案内容の具体性など、対応の質も重要な判断材料になります。
【ステップ3】通訳者の選定・契約
提出されたプロフィールや実績を吟味し、契約内容(業務範囲、料金、キャンセル規定など)を双方でしっかりと確認し、書面で契約を締結します。
【ステップ4】事前資料の共有(成功の鍵)
通訳の品質は、事前情報の量と質で9割決まると言っても過言ではありません。会議のアジェンダ、プレゼン資料、専門用語の対訳リスト、参加者名簿、関連する過去の資料などを、可能な限り早く、そして多く共有してください。
「資料が多すぎて困る」ということは絶対にありません。むしろ情報が少ないことが最大のリスクです。通訳者はプロの秘密保持義務を負っていますので、機密情報であっても安心して共有してください。理想としては、開催日の1〜2週間前に第一弾の資料を共有することです。
【ステップ5】当日の簡単な打ち合わせ
本番開始の15〜30分前に、通訳者と当日の流れや目的を最終確認します。「この部分の発言は特に強く伝えたい」「この参加者の意見を重点的に聞きたい」といった要望を伝えることで、より意図に沿った通訳が期待できます。
最後に、契約書に含めるべき点を挙げます。
支払い条件とキャンセル料金について
契約時には、後々のトラブルを避けるために、以下の点を必ず書面で確認しましょう。
支払い条件
請求書の発行タイミングと支払いサイクル(例:業務完了後の翌月末払いなど)を明確にします。
キャンセル規定
通訳者はその案件のために長期間スケジュールを確保し、他の仕事を断っているため、直前のキャンセルにはキャンセル料が発生するのが一般的です。
例えば「7日前〜4日前:50%」「3日前〜当日:100%」といった規定が明記されているかを確認しましょう。これは、プロフェッショナルな仕事に対する当然の対価であり、業界の標準的なルールです。
秘密保持契約(NDA)
通訳会社との契約には通常、秘密保持条項が含まれていますが、フリーランスと直接契約する場合は、別途NDAを締結することをおすすめします。これにより、機密情報の取り扱いに関する双方の認識を合わせることができます。
通訳の料金は高い?
通訳のスキルによって料金に差が出るのは分かりますが、実際に通訳の料金表を見た時に、「高いな~」と思われるかもしれません。例えば、Cレベルのフリーランスの方に8時間依頼した場合でも相場は3~5万円です。Sクラスだと、12万円~となっています。
一見高く見える通訳者の相場ですが、実際には適正な価格と言えます。それには、主に4つの明確な理由があります。
専門性と経験値という「無形の資産」
前述の通り、通訳者が長年かけて培ってきた専門知識や、失敗の許されない現場を乗り越えてきた経験そのものが、付加価値として価格に反映されています。
通訳形式に伴う「心身への負荷」
特に同時通訳は、極めて高い集中力と認知能力を要するため、心身への負荷が膨大です。15分で交代しなければパフォーマンスが維持できないほどの過酷な作業であり、その難易度が料金に反映されるのは当然と言えます。
見えない拘束時間「プロフェッショナルとしての事前準備」
これが最も重要な要素です。通訳者の仕事は、現場にいる時間だけではありません。「30分の通訳のために30時間の準備をする」と言われるように、その準備は多岐にわたります。
企業のウェブサイトやIR情報を読み込み、過去の議事録や製品カタログを研究し、想定される専門用語の対訳リストを作成し、さらには主要な登壇者の過去の発言やクセまで調査することもあります。この準備こそが本番の質を担保しており、半日・1日単位の料金体系が基本となっている最大の理由です。
市場における「需要と供給のバランス」
最先端技術やニッチな分野、そして希少言語に対応できる通訳者は、市場全体で見ればごくわずかです。その限られた専門家に対して需要が集中するため、必然的に価格は上昇します。
このように、通訳者というのは心身ともにかなり負荷のかかる大変なお仕事であることが分かります。また毎日仕事があることは稀なため、一般的にも年収が300万円~500万円の業界と言われ、技術職の中では比較的報酬が低めの部類に入ります。
こうした背景を知っておくことで、実際に依頼する通訳者さんの苦労を理解でき、良いコミュニケーションを図ることができるでしょう。
通訳相場 フリーランスまとめ
通訳者の手配は、単なる「外部業者への発注」ではありません。言葉と文化の壁を越え、自社のビジネスを成功に導くための「戦略的パートナーシップ」を築くプロセスです。
フリーランスを使うか、通訳会社に依頼するかを決める上で、以下の3つの要点を振り返りましょう。
- 「価格」ではなく「価値」で選ぶ 目先の費用だけで判断するだけでなく、その通訳者がもたらす「正確な意思疎通」「円滑な交渉」「ビジネスチャンスの創出」といった価値に対して投資するという視点を持ちましょう。
- 案件の「重要度」が依頼先を決める まずは、その会議や商談が自社にとってどれだけ重要かを冷静に評価してください。その上で、リスクの低い案件は信頼できるフリーランスに、企業の将来を左右するような重要な案件は実績豊富な通訳会社に、と戦略的に使い分けるのが成功の秘訣です。
- 最高のパフォーマンスは「協業」から生まれる 通訳者に「丸投げ」するのではなく、チームの一員として迎え入れ、十分な情報を提供し、プロフェッショナルとして尊重する。この「協業」の姿勢こそが、通訳者の能力を120%引き出し、最終的に自社の利益に繋がる最も確実な方法です。